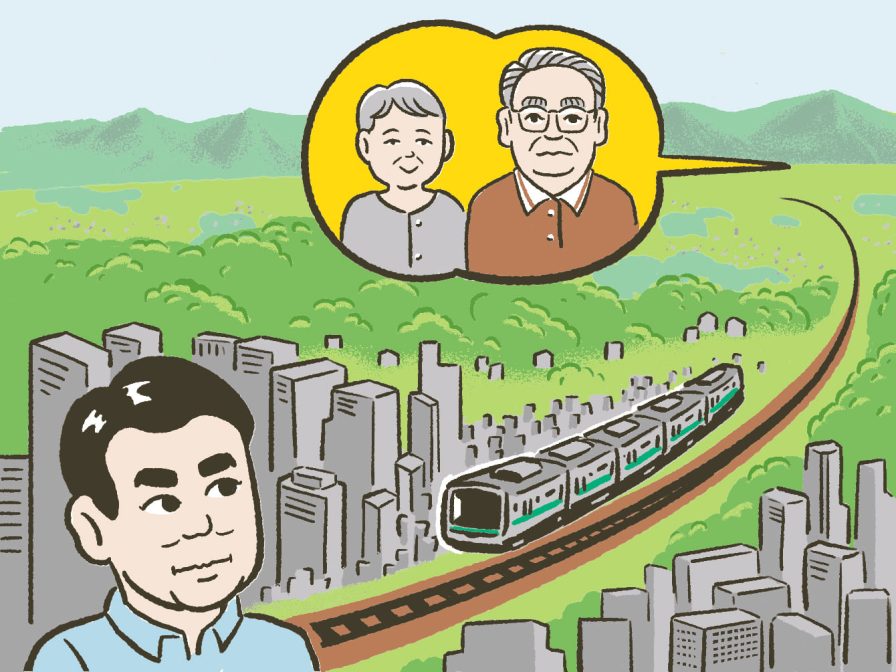親が高齢になってくると、避けられない介護の問題。実際、85歳以上の約6割が要介護認定を受けていることをご存じでしょうか。
数字だけを見ると「まだ先の話だから」と思うかもしれませんが、疾患や状況によってはある日突然介護が始まることも少なくありません。
介護費用はいくらかかる?負担は子どもが支えるべき?親のお金はどう管理する?などなど、誰もが気になる親の介護とお金の問題について、ファイナンシャル・プランナーの柳澤美由紀さんに聞きました。
突然始まることも多い介護、早めに備えるのが吉
――そもそも親の介護はどんなふうに始まることが多いのでしょうか?
もっとも多いケースは認知症です。徐々に進行していくにつれ、介護が必要になってくるケースですね。
介護が必要になる主な原因
1位:認知症
2位:脳血管疾患(脳卒中)
3位:骨折・転倒
※厚生労働省「2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況」「介護の状況」より
また、脳血管疾患や骨折などが原因だと、「ある日突然倒れて、その日から急に介護が始まる」こともあります。特に骨折や転倒は高齢になると誰にでも可能性があるため、親が60~70代になったら介護を意識し始めても決して早すぎることはありません。
▶︎認知症について知りたい方はこちらの記事もチェック
認知症になってからでは遅い! 親が元気なうちに備えるお金の対策
――介護の準備は何から始めればいいですか?
まずは「具合が悪くなったら、動けなくなったらどうしたいか」を親に聞いてみること。自宅で過ごしたいのか、施設に入りたいのかなどの希望を把握し、そのうえでお金の管理をどうするか話し合いましょう。
――介護費用を親本人と子どものどちらが払うのかも、相談したほうがいいですよね。
原則として、介護費用は親本人の収入と資産でまかなうようにしてください。一時的なサポートだけならまだしも、子どもがすべての負担を背負ってしまうと、ご自身の生活が立ち行かなくなる恐れもあります。
――えっ。そんなに多額になるんですか!?
実際に親の介護費用が重荷となり、キャッシング等で介護費用を捻出していた人がいました。「公的介護施設は簡単に入居できない」と思いこみ、週5日ショートステイ(短期入所サービス)を利用して、働きながら親を介護していました。ただし、その費用が月に13~14万円ほどかかっていたので、次第に家計の負担が重くなっていったのです。
――そんなに負担が大きいといつかは破綻しますよね。でも、親にお金がなければ、子どもが介護をするか、代わりにお金を負担して介護サービスを受けるしかないのでは?
そんなことはないんです。特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)といったいわゆる公的介護施設は、要介護度や居住環境など介護の必要性の高さによって優先順位が決まるため、親の収入や資産が少なくても入居できます。特定入所者介護サービス費などの低所得者向けの負担軽減制度や、生活保護を受ける手段もあるので、「親にお金がないから介護を受けられない」なんてことはほぼありません。先ほど話した方も、ケアマネージャー(介護支援専門員)さんに経済的な事情を相談したところ、トントン拍子で親御さんの施設入所が決まり、子の介護負担をゼロにすることができました。
――なんでも早めに相談したほうがよさそうですね。
はい。公的な介護費用については、地域包括支援センター※に相談するか、すでに介護担当がついている場合はケアマネージャーさんに聞いてみてください。子ども側が何もかも背負いこまないようにすることが肝心です。
※高齢者の健康や生活全般に関する相談を受け付けている無料相談窓口。各市区町村に設置されており、介護に関するアドバイスや手続きを行ってくれる
介護費用を補うため民間の介護保険に加入するという手も
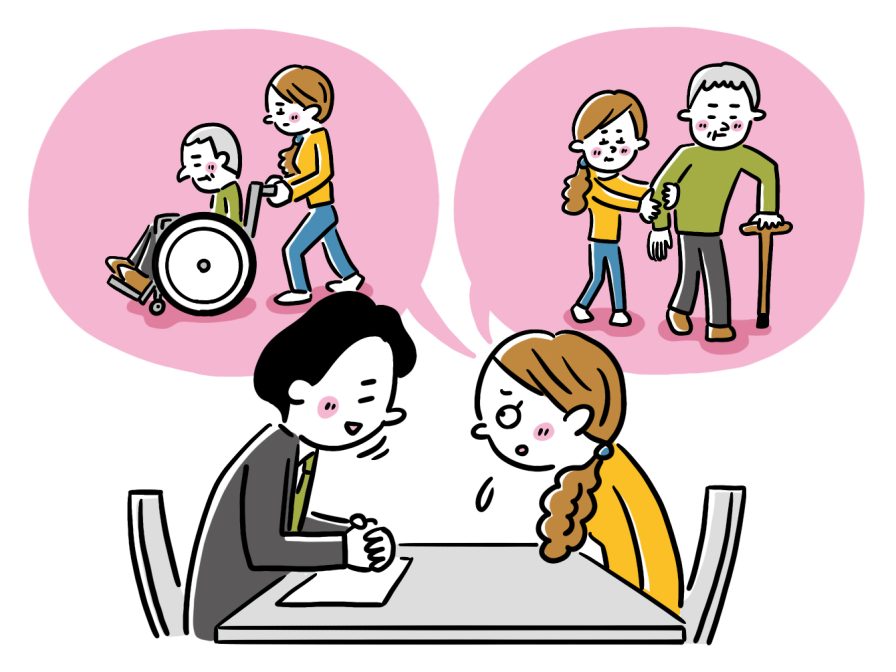
――おおよその介護費用ってどれくらいかかるものなのでしょうか?
生命保険文化センターの調査によると、介護発生時にかかる介護費用は50万円弱で、月々の費用は9万円程度です。
介護費用の平均
- 介護発生時にかかる費用:平均47万円(公的介護保険の利用あり:46万円/公的介護保険の利用経験なし:68万円)
- 月々の費用:平均9万円(在宅:5.2万円/施設:13.8万円)
※生命保険文化センター「2024年度 生命保険に関する実態調査」より
――結構かかりますね。子ども側ですべてを負担するのは無理でも、多少はサポートすべきなのかなと思ってしまいますが。
子どもが一時的にサポートする場合なら、介護発生時から半年間ほどの期間をカバーできる100万円ほどあれば十分です。親本人の備えとしては、在宅介護で乗り切るのであれば300万円程度、施設入所も視野に入れるのであれば500万円程度備えておきましょう。ただ、介護施設の利用料はエリアや施設のクオリティによって入所一時金・月額利用料ともに格差があります。預貯金で足りない場合、民間の介護保険で備える方法もありますよ。
――民間の介護保険は、子ども側で手続きして加入することもできるんですか?
できますよ。その場合は親を被保険者にして、子どもは契約者で保険料を払う形態にします。その場合、掛け捨て型にすれば負担を抑えられますし、親には「万が一のために入っておいていい?」と言っておけば、嫌がられることは少ないでしょう。
親自身が介護保険に入る場合は、介護の備えと同時に資産形成ができる商品を好まれる方が多いですね。要介護状態にならなくても保険金を受け取れる商品だと、老後資金の備えに回せますから。
――認知症保険というのもありますよね。介護保険とどちらがよいでしょう?
認知症保険は、認知症以外の要介護状態だと対象外になるため、保障の範囲が限定されます。
脳血管疾患や骨折による介護など、幅広い要介護状態に備えるのであれば介護保険が適しているでしょう。なお、オプションで認知症特約を付帯できる介護保険もあるので、金融機関に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
第四北越銀行よりお知らせ
第四北越銀行ではお客様のニーズに合わせ幅広く介護保険をご提案できるほか、“使わなかった保険料が戻ってくる”タイプの積立型介護保険もご用意しています。お気軽に窓口までご相談ください。
お問い合わせ先はこちら
公的介護サービスと介護保険などをフル活用すべし
――介護とお金の問題に関して、その他に子どもができる備えはありますか?
親の介護における子どもの役割は、公的介護サービスを円滑に受けるための調整を行うこと。いざというときにすぐ動けるよう、親と話し合いをしつつ、あわせて情報収集をしておくのが大切です。
親の介護に向けた備え
- 介護に関する親の希望を聞いておく
- 親の財産・収入を把握しておく
- (必要に応じて)民間の介護保険の加入を検討する
- 自分の勤務先の介護制度を確認しておく
- 地域包括支援センターの連絡先や担当者を確認し、公的介護サービスを受ける際のおおまかな流れを把握しておく
- 公的介護施設以外の民間施設・サービスを調べておく
公的介護施設の入居には所定の要件に応じた優先順位があります。状況によっては、すぐ入居できないこともあるでしょう。必要に応じて民間の老人ホームにつなぎ入所することも念頭に、各地域の施設やサービスを調べておくようにしてください。